日能研流新4年生のノートの準備と使い方

日能研流新3年生のノートの準備と使い方まとめ
「自走学習」ができるようになると、親はとても楽になると思います
自走学習のための、準備としてノートの取り方を徹底してくことが重要です
授業で見聞きした事をしっかりとノートに整理して持ち帰ってくることで、振り返りの制度が上がりますね
その作業を繰り返すことで、ひと足早く自走学習の準備に入りましょう
日能研ノートの準備
新4年生でも、新3年生の時と同様に日能研ノートを使って行きます
この日能研ノートを購入して利用するだけでも、適正ノートの選択作業から解放されるのは嬉しいことです
授業に合うノートってどんなノートだろう?って悩んじゃいますよね
そういった意味では、日能研ノートを使っておけばOKという安心感はありますので、ぜひ活用して行きましょう
おさらいになりますが、日能研ノートは8mmの方眼ノートになります
学習効率を考えての方眼ノートです
私は、子供からの質問を受けて説明する時も方眼ノートを使って説明します
実は、仕事でもメモや情報を整理するためのノートは方眼ノートです
ノート選びで迷ったら、ひとまず方眼ノートを準備してあげれば大丈夫だと思います
次に、ノートの色分けを考えて行きましょう
日能研の方眼ノートは、青色、紫色、黄色、緑色とサイズが小さなオレンジ色の5色に分けられています
この色は科目毎で色分けして管理するのにとても便利です
日能研では、科目毎にイメージカラーがあるのでそのイメージカラーに合わせてノートを準備するのが良いでしょう
青色は、算数のカラーです
紫色は、国語のカラーです
黄色は、理科のカラーです
緑色は、社会のカラーです
このカラーバリエーションで準備しておくと、子供にとっても学習時にどのノートを使えば良いのか?という時間ロスから解放されます
新3年生の頃は、算数と国語の2科目だったので青色と紫色の2色を利用していました
新4年生からは、科目が増えて4科目になり黄色と緑色が追加になりますね
これでノートの準備は良いので、次に使い勝手を工夫して行きます
ノートに合わせたラベルの準備になります
我が家が使ってるラベルは、次のラベルになります
ノートは授業ノートと振り返りノートが、各科目毎に2種類ありますね
さらにノートは贅沢に使って行きましょうと新3年生のノートの準備と使い方で書きましたね
そのため、多くのラベルが必要になってきます
手書きでも良いですが、面倒なのでPCを使ってサクッと印刷しちゃいます
また、一度作ってしまえばその雛形を使って何度でも印刷できますし使い回しも楽です
「らくぷり」というアプリを使って、楽しましょう
とても簡単でシンプルな使い勝手なので、抵抗なく作成できると思います
とても簡単でシンプルなので、使い勝手は良いと思います
国語ノートの準備と使い方
国語のノートは、8mm方眼ノートを横にして利用します
さて、縦21マス・横28マスの1ページをどのように使うのかが重要ですね
我が家では次の様に区分けをして利用しています
ノート利用の工夫の参考になればと思います

【①日付】
必ず「日付」を記載します
授業進捗管理の主軸にもなるので、意外と日付情報は重要です
【②項番】
テキストに沿った「項番」を記載します
この項番がないと、受講内容を振り返るとき迷子になります
【③タイトル】
1行にしっかりと「タイトル」を記載します
タイトルの理解も今後重要になってきます
なぜなら、その文章の最大要約情報がタイトルになるので、意識づけが重要です
【④板書(ばんしょ)スペース】
新4年生ともなると、ただ授業を聞いてくるだけでは物足りなくなります
しっかりと授業中の講師の板書情報を持ち帰ってくる必要があります
この板書情報ないと、振り返りの際に講師の授業方法に沿ったアドバイスができなくなります
【⑤疑問(ぎもん)スペース】
当然、授業内で知らない言葉や意味がわからないものが出てきます
ちょっとした疑問や気になった事をメモする癖をつけておくと、今後の自走学習に向けて良いきっかけになります
算数ノートの準備と使い方
算数のノートは、8mm方眼ノートをそのまま縦にして利用します

【①日付け】
国語のノートと同様で、必ず「日付」を記載します
授業進捗管理の主軸にもなるので、意外と日付情報は重要です
【②タイトル】
国語のノート同様に大きく記載します
算数では2行使って記載して行きましょう
特に新4年生は、文字を丁寧に記載するように心がけていくと良いです
文字を丁寧に書くことへの早めの意識づけが重要です
【③サブタイトル】
1行にサブタイトルを記載します
ひとマスに1文字記載するように心がけると、文字が見やすく振り返りの時も楽になります
【④項番】
テキストに沿った項番を記載します
この項番がないと、受講内容を振り返るとき迷子になります
【⑤理解度チェックa】
わからなかった問題には、項番にバツ(X)をつける様にします
同時にテキストにもバツ(X)をつけておくことで、振り返るときに連動しやすくなります
学習時の時短効果が期待できます
【⑥板書ルール】
国語同様に授業を聞いてくるだけでは物足りないので、しっかりと授業中の講師の板書情報を持ち帰ってくる必要があります
その際に文字の色のルールを決めておきます。
黒板に白色チョークで書かれた文字は、鉛筆でノートに記載します
黒板に赤色チョークで書かれた文字は、赤鉛筆(赤ペン)でノートに記載します
黒板に黄色チョークで書かれた文字は、黄色でノートに書くと見えにくいので青鉛筆(青ペン)で記載します
このように文字を色分けすることで、講義内容の重要ポイントを振り返りやすくなります
【⑦計算スペース】
新4年生になると、算数は途中の計算式も重要になります
受験対策として、途中式を残す癖は今のうちからつけておく必要があります
今後回を重ねる毎に、計算は複雑になってきます
回答が間違っていた場合でも途中式がないとどこのポイントで間違えたのかがわからなくなるので途中式は重要ですね
【⑧解き方の理解】
子供の中には、ひらめきやオリジナリティ溢れる解き方をする子供もいます
そこで、自分の解き方と先生の解き方に違いがあった場合は、板書情報や解説をメモする必要があります
塾講師の教え方と別の方法で家庭でレクチャーすると、子供が混乱するので要注意です
【⑨習った方法で解く】
大人は中学、高校、大学と教育課程を経験しており、答えを出すための近道を多く知っています
でも、中学受験をする子供は小学生なので、その年齢や学年に合わせた解き方があります
そのため、講師の解き方をしっかりとトレースしておかないと、後々軌道修正が大変になるので要チェックです
【⑩理解度チェックb】
問題番号への理解度チェックですが、子供は書けたと理解できたということを勘違いしがちです
記憶が新しいうちに、理解度レベルを自己判断させておくと習熟度判断に使えるので、可能であれば付ける努力をしてみると良いです
社会ノートの準備と使い方
社会のノートは、算数ノートと同じで大丈夫です
理科ノートの準備と使い方
理科のノートも、算数ノートと同じで大丈夫です
ノートの準備と管理方法
自走ができている子供は、少しずつ手を離しても大丈夫ですが・・・
我が家は、まだまだ手放せそうにないので並走し続けます
ノートの取り方を子供に伝えると、初めのうちは記憶が新しいのでルールを守ってノートを取るのですが
2回、3回と回を重ねるたびにルール無用の落書きノート状態になります
そうなると、自宅で見返したときに何をやったのかを振り返ることができなくなります
そのためにも、ルール通りにノートを取ることができているかのチェックは重要です
イタチごっこにはなってしまいますが、ルールからズレているところは常に軌道修正して行きましょう
ちなみに我が家は、早速の落書き状態で親の心が折れそうですが頑張ります
ゴールは「自走学習」です
その前段階として、授業の内容を聞き、理解し、重要箇所を持ち帰ってくるという学習の基本作業を身につけるため、このノートの取り方を徹底すると良いでしょう
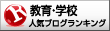











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません